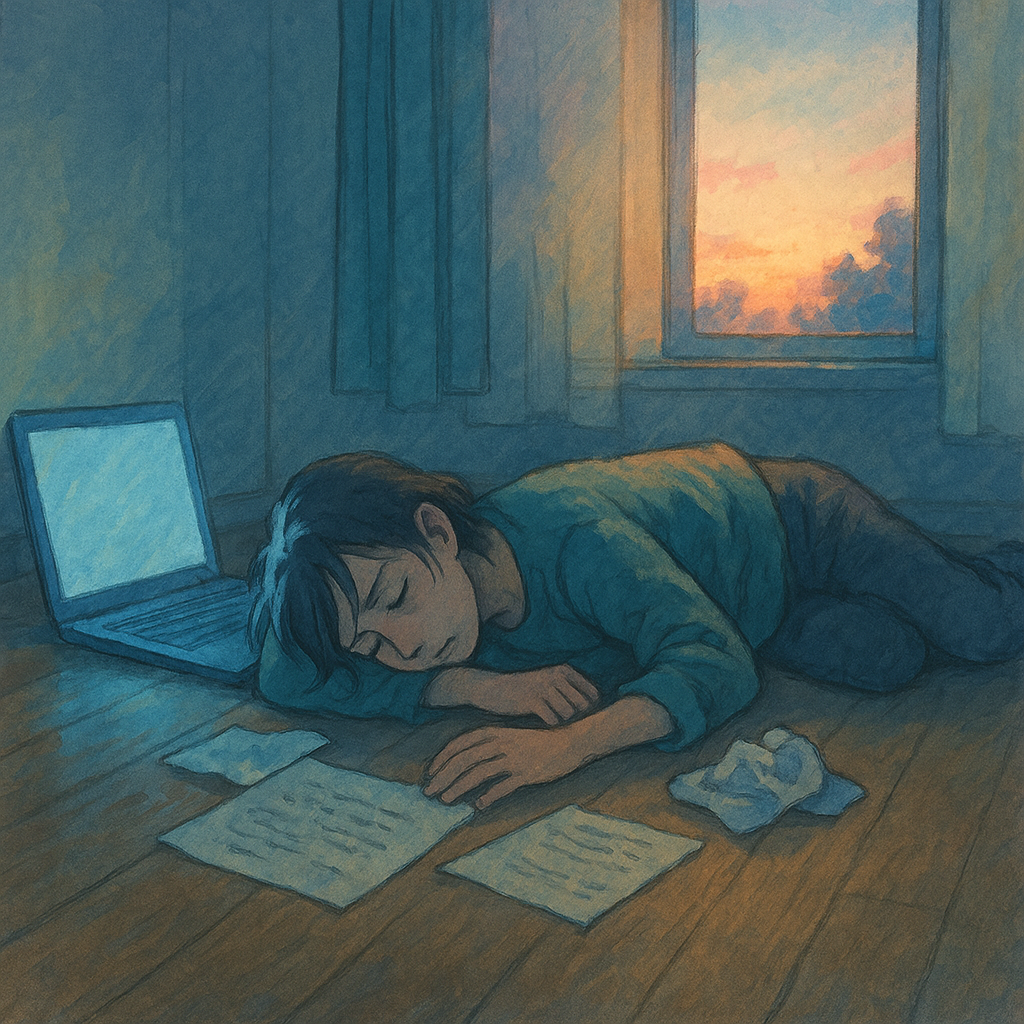「知恵を出せ。知恵がなければ汗をかけ。汗もかけないなら──血を流せ。」
これは、かつて私が身を置いていた職場で繰り返し耳にした言葉でした。
でも私は、ある日ふと気づいたのです。
──私はもう、とっくに“血を流していた”のです。いや、それは比喩ではありません。
体を壊し、意識を失いかけながら、命を削るように働いていたという現実そのものでした。高次脳機能障害という“見えない壁”と向き合いながら、私は「働くこと」と「生きること」の境目を失っていったのです。
私が流してきた「血」とは何か
深夜の障害対応:記憶が飛ぶ中でも
めったにないことでしたが、病後、2〜3度ほど真夜中に呼び出されることがありました。
記憶障害によって、ほんの少しの衝撃で作業の全体像が消えてしまう。
数分で終わるはずの作業が、何時間かかっても終わらない。
それでも止められなかったのは、「私しか対応できる人がいない」という責任感から。
作業を止めれば、記憶ごとすべてがリセットされてしまう──そんな恐怖がありました。
「這いつくばって作業していた」──これは本当にそのままの意味です。
椅子に座っていられないほどの頭痛や過呼吸、身体の重さ。
床に横たわりながら呼吸を整え、少しでも回復したら、また椅子に戻る。
それを何度も繰り返していました。
ほんの数分休んだつもりが、気づくと1時間が経っていることもありました。
本当に、気絶していたのかもしれません。
それでも私は、立ち上がって作業を続けました。
努力の痕跡が見えないとき、私たちはそれを“怠慢”と決めつけていないでしょうか?
補助ツールの整備:見えない努力
私の障害は「見えないと忘れる」という特性を持っています。
そのため、作業の全体像も細部も、すぐに霧の中に消えてしまうのです。
私は、数々の工夫でそれを乗り越えようとしてきました。
- 作業工程を可視化する独自のメモ術
- 記憶を呼び起こすためのルーティン化
- Evernoteによる第2の記憶装置
これらはすべて、誰にも見えないところで、膨大な時間と試行錯誤を重ねて築いたものです。
曖昧な指示の構造化:混乱の中でこそ発揮される力
お客様自身が「何をどう指示すべきか分からない」──
そんな状況でも、私は物事を構造化して整理する力を活かしてきました。
脳に障害を負っても、この能力だけは失われなかったのです。
曖昧な依頼をかみ砕き、言葉にならない混乱を整理し、システムを守る。
圧倒的な存在感があった、と言われることもありました。
不当な評価:のんびりしている? 本当に?
障害のある私は、健常者と同じスタートラインに立つだけで莫大なエネルギーが必要です。
マイナスをゼロにするための努力、そこからさらに価値を生み出す努力。
人の何倍もかかる道のりを、私は日々歩んできました。
しかし、私の努力は可視化されず、
「のんびりしている」「当事者意識がない」と責められる現実がありました。
私が得たもの、失ったもの
得たもの
- 現場からの絶対的な信頼
障害があっても、「この部分なら任せられる」という無言の信頼が確かにありました。
それは“見せ方”や“伝え方”によって築いてきたものでした。 - 構造を生み出す力
私は物事を「点」ではなく「流れ」で捉えることができます。
これは、障害を負っても変わらなかった自然体の強みです。 - “できない人の痛み”に寄り添える視点
できないことには、理由がある。
その理由に想像力を持てるようになったことは、私にとっての財産です。 - 未発掘だった能力
能力が落ちたのではなく、別の能力が目覚めただけかもしれない──
そんな可能性を、私は今、信じています。
失ったもの
- 健康、安心、尊厳
記憶力、注意力、耐久力──すべてを同時に失った日々。
それに伴って、社会的信頼も大きく揺らぎました。 - 正当な評価と報酬
障害があるという理由だけで、「このくらいでいい」と評価されることがありました。
でも、私には“人にできないこと”が、確かにできる。 - 積み重ねてきた信用の一部
「障害を負っても変わらない」と言ってくれる人もいれば、
「もう使えない」と言う人もいた──それが現実でした。
でも、無駄じゃなかった
あの夜、床に倒れ込むようにして作業を続けていた私に、
「それでも無駄じゃなかったよ」と伝えてくれる誰かが、もしあったなら──。
今なら、その“誰か”に、私自身がなれる気がしています。
臥薪嘗胆──いまは報われなくても、いつか日の当たる日がくる。
そう信じて、自分の持てる力を磨き続けてきました。
就労移行支援という新しい場で、ようやく私は「血を流した意味」に触れました。
私の力は、確かに誰かの役に立っていた。
あの痛みがあったからこそ、
「誰かの痛み」にも気づけるようになった。
あの孤独があったからこそ、
「寄り添う」ということの本当の意味がわかるようになった。
あの屈辱があったからこそ、
「誠実に働ける場所」がどうあるべきか、明確に見えるようになった。
新しい場所を探しています
光を放つとは、誰かを照らすこと。
でもそのためには、自分の光を消してはいけない。
私は、今ようやくそう思えるようになってきました。
私が望むのは、「障害があるかないか」ではなく、
「どんな力を持ち、どんな可能性を秘めているか」で判断される場所。
無理なことは無理。でも、できることは確かにある。
その“当たり前”が当たり前として通じる場所で、
私は、私らしく“光を放ちたい”のです。