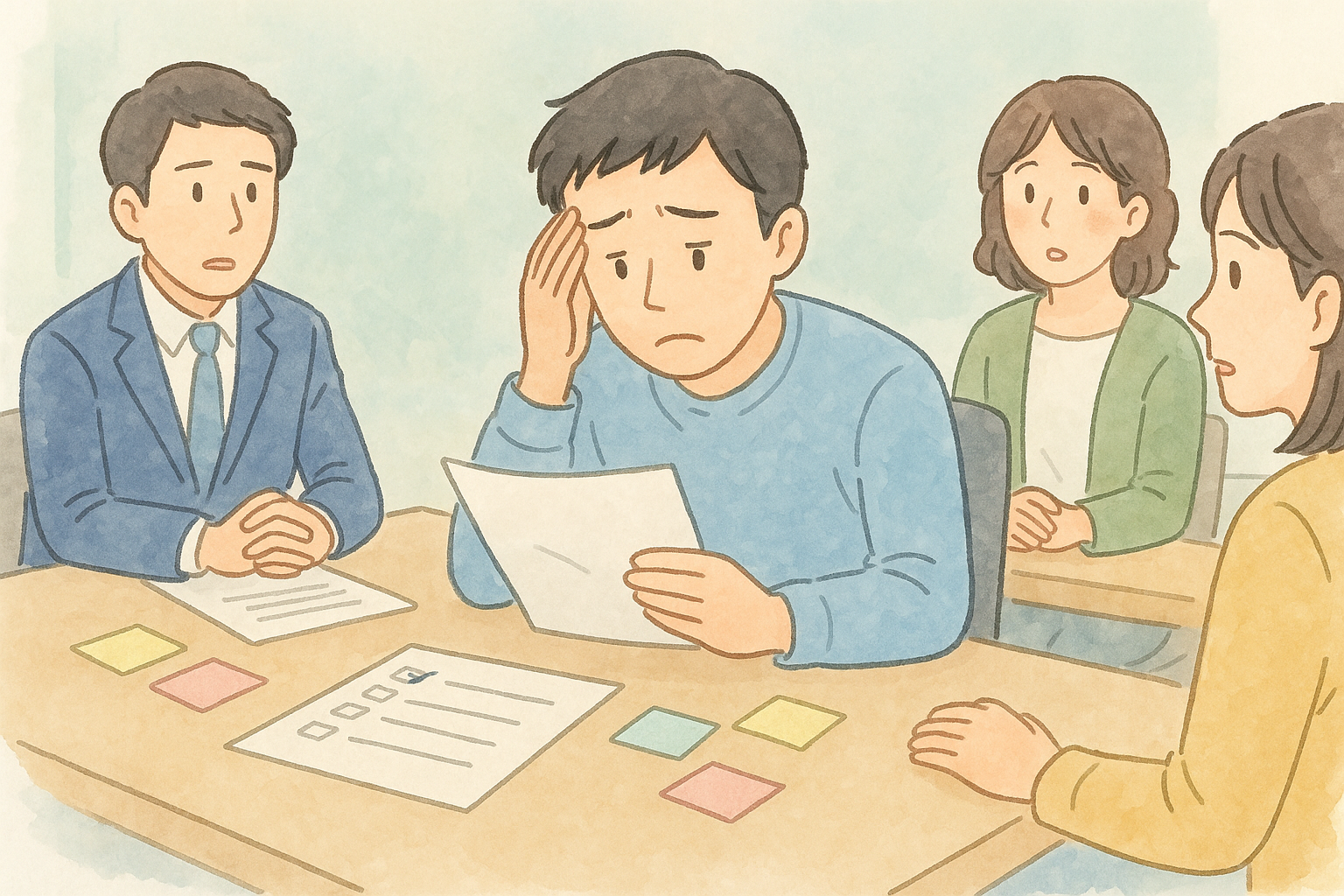“くどさ”はなぜ迷惑と思われるのか
「また同じことを聞いてる」「しつこいなあ」と感じたことはありませんか?
職場や家庭で、何度も同じ質問や確認を繰り返されると、どうしても「時間がもったいない」「作業が進まない」とストレスになるものです。
この記事では、そうした“くどい”行動の裏にあるものを考えてみたいと思います。
本当に「ワガママ」なのか?――見えない背景
“くどい人”と聞くと、「空気が読めない」「自己中心的」といった印象を持つかもしれません。
ですが、その“くどさ”が本当に本人のワガママから来ているのでしょうか?
特に、記憶障害や高次脳機能障害を持つ人の場合、
何度も確認しないと本当に忘れてしまう、あるいは「忘れていたことすら覚えていない」状態に陥ります。
彼らの“くどさ”は、「失敗したくない」「迷惑をかけたくない」「見下されたくない」
――そんな切実な思いから生まれる“防衛反応”なのです。
受け止めてほしい「不安」と「恐怖」
当事者が何度も確認する背景には、
- 失敗への強い恐怖
- 過去のミスや叱責のトラウマ
- 「またやったのか」と見下される不安
があります。
「くどい」と言われるたびに、“もう質問しちゃいけないのかも…”と萎縮し、
本当に必要な確認さえできなくなり、結果としてさらに大きなミスにつながる――そんな悪循環も起こります。
迷惑を減らすための工夫――“折衷案”のすすめ
だからといって、周囲の負担や効率を無視して良いわけではありません。
「くどさ」も、「迷惑」も両方事実です。
そこで大切なのが**「仕組み」や「工夫」で折り合いをつけること**です。
例えば…
- 確認事項は書面やチャットで一元管理する
- 質問タイムやチェックリストを用意して、必要な確認を事前にまとめる
- どうしても不安なときは「3回までOK」などルールを決める
こうした“見える化”や“ルール化”によって、
当事者も周囲も安心して働ける環境を一緒に作ることができます。
「迷惑」を超えて、共に働くために
“くどさ”は、たしかに周囲に負担をかけることもあります。
でも、それは「怠け」や「適当さ」から来るものではありません。
「なぜ何度も確認するのか?」
「なぜこんなに準備するのか?」
――その“背景”に思いを寄せてみてください。
配慮や工夫が少しでも広がれば、
「しつこい」ではなく「誠実で安心な人だ」と認識が変わる日が来るかもしれません。
一緒に“違い”を責め合うのではなく、“違い”の中で安心して働く方法を、みんなで見つけていけたら――
それが本当の「合理的配慮」の第一歩だと、私は信じています。
【あとがき】
あなたの職場やご家庭にも、「何度も同じことを確認する人」はいませんか?
「迷惑だな」と感じたときこそ、その“水面下の努力”に想像力を向けてみてください。
そして、もし自分自身が“くどい”と言われて悩んでいるなら、
「それは誠実さの証」と胸を張ってほしいと思います。
【補足】
この記事は、記憶障害・高次脳機能障害などの“目に見えにくい困難”を持つ方と、周囲の方々双方に役立つことを願って書きました。