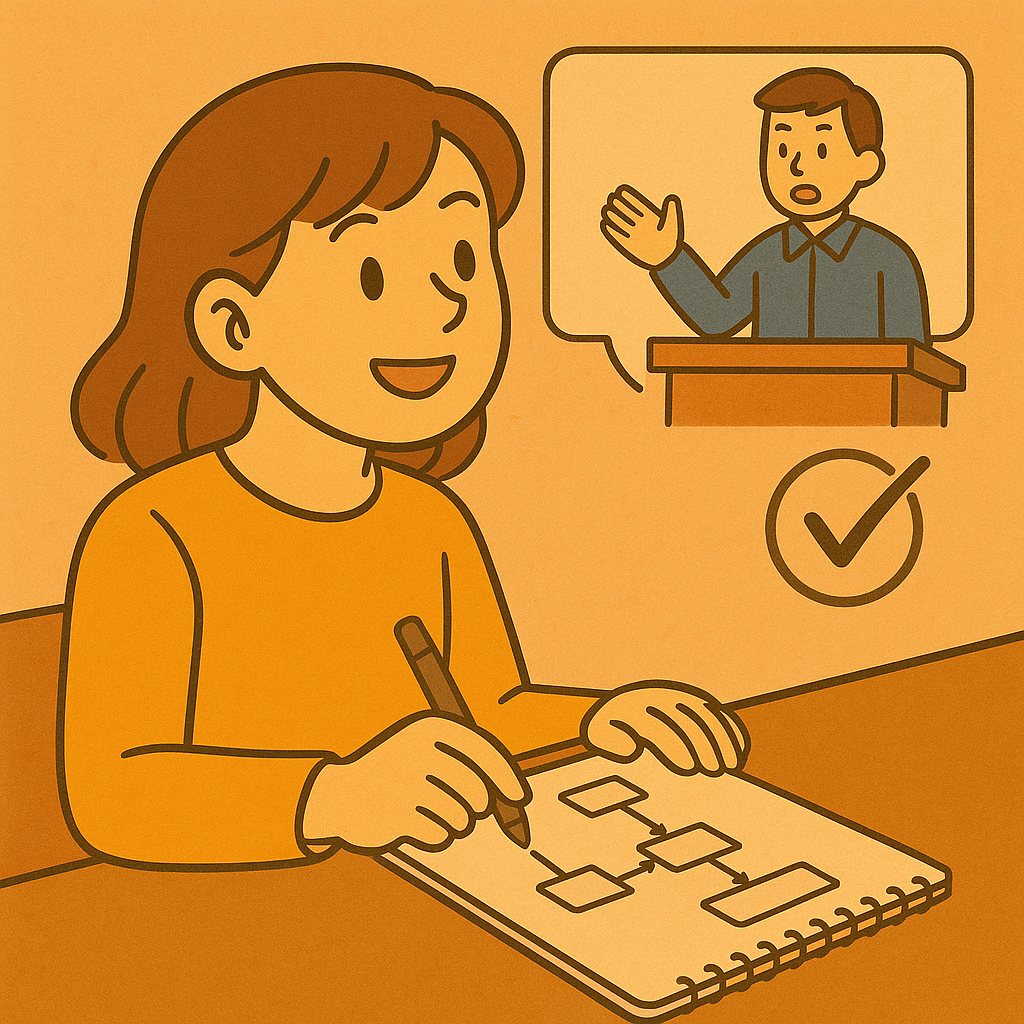🟦 はじめに──「聞いたそばから抜ける」現実と向き合って
私は記憶障害を抱えています。
特に困るのが、「人から言われたことをすぐに忘れてしまう」ことです。
たとえば、会議で話を聞いても、終わった瞬間にはもう半分以上が頭から抜けていたり、
「●●しておいて」と言われたことを、数分後にはすっかり忘れていたりする。
それでも仕事をしたい。人の役に立ちたい。
だから私は、自分の脳に合った“聞いた内容を確実に残す方法”を、試行錯誤の末に見つけました。
🟦 フローチャート式の手書きメモ──文章ではなく「構造」で残す
私は一時期、会議中にパソコンで文字を打ちながらメモを取ろうとしていました。
タイピング速度には自信があります。10分で1000文字以上は書けます。
でも、それでも無理でした。
なぜなら、口頭で伝えられる情報は「清書された文章」ではないからです。
- 脱線する
- 主語が省略される
- 時系列が前後する
- 話の目的が見えないまま終わることもある
そんな情報を聞きながら同時に整理して入力する──それは、脳の処理構造として現実的に不可能でした。
🟦 私のメモは「縦方向のフローチャート」が基本です
私が使っているメモの書き方は、縦方向に流れるフローチャートです。
上から下へ、単語を順番に矢印でつないでいきます。
なぜなら、「話の流れ」や「作業の手順」は、時間とともに縦に流れる感覚があるからです。
横に並べて書くと見落としやすい「順番」や「因果関係」も、縦にすると自然に把握できます。
たとえば、こんなイメージです:
(上司の指示)
↓
(●●という作業)
↓
(△△までに提出)
↓
(完了報告をメールで)
このようにすると、「何をするか」だけでなく、
その流れの中で“今どこにいるか”が、目で見てすぐに分かるようになります。
さらに、途中の抜けも見つけやすく、記憶障害の私にとっては大きな安心材料です。
🟦 「全部は無理」でも「抜けを防ぐ」は可能
私はある時、はっきりと気づきました。
全部を記録するのは、無理だ。
でも、“やることを忘れない”ようにするのは、できる。
この気づきが、記録方法の転換点でした。
完璧を目指すのではなく、自分が忘れると困ることだけを確実に残す。
それがフローチャート式のメモです。
🟦 一番大事なのは「確認すること」──これができれば何も怖くない
でも、メモを取るだけでは足りません。
私はメモを書き終えたあと、必ずこう言います:
「このメモ、私の理解で合っていますか?」
この確認の一言があるかどうかで、仕事の精度はまったく変わります。
指示をくれた相手も、自分の言葉を客観的に見直す機会になります。
お互いの誤解や思い込みを、その場で修正できる唯一の手段です。
🟦 新しい働き方に向けた準備期間中に──確認は“実践スキル”の一部
私は今、新しい働き方に向けた準備期間中にあります。
この中で、私は「確認すること」の大切さを強く感じるようになりました。
誰も「なんで確認するの?」なんて言いません。
むしろ、自分から確認できる人ほど「実践に近づいている」と私は感じています。
(※これは私の体験に基づいた個人的な印象です)
🟦 AIや録音技術はどうか?──使える場所と、使えない場
録音+AI書き起こしという方法もあります。
私も試したことがありますが、今いる学びの場では使っていません。
なぜなら、ここは“成長のための訓練の場”だからです。
周囲との公平性、訓練としての意味、自分で考える力を養うこと──
それを放棄するような使い方は避けるべきだと私は考えています。
🟦 最後に──「確認する勇気」が、安心と信頼を生む
私は障害があります。
でも、「確認すること」を恐れなければ、大きな失敗は防げます。
私にとって、確認とは“自信がない証拠”ではなく、
“安心して仕事ができる状態を作るための行為”です。
そしてこれからも私は、紙に手書きで単語を結び、フローチャートを描き、
「この理解で合っていますか?」と尋ねていくつもりです。
その繰り返しの先に、「安心して働ける場所」があると信じて。