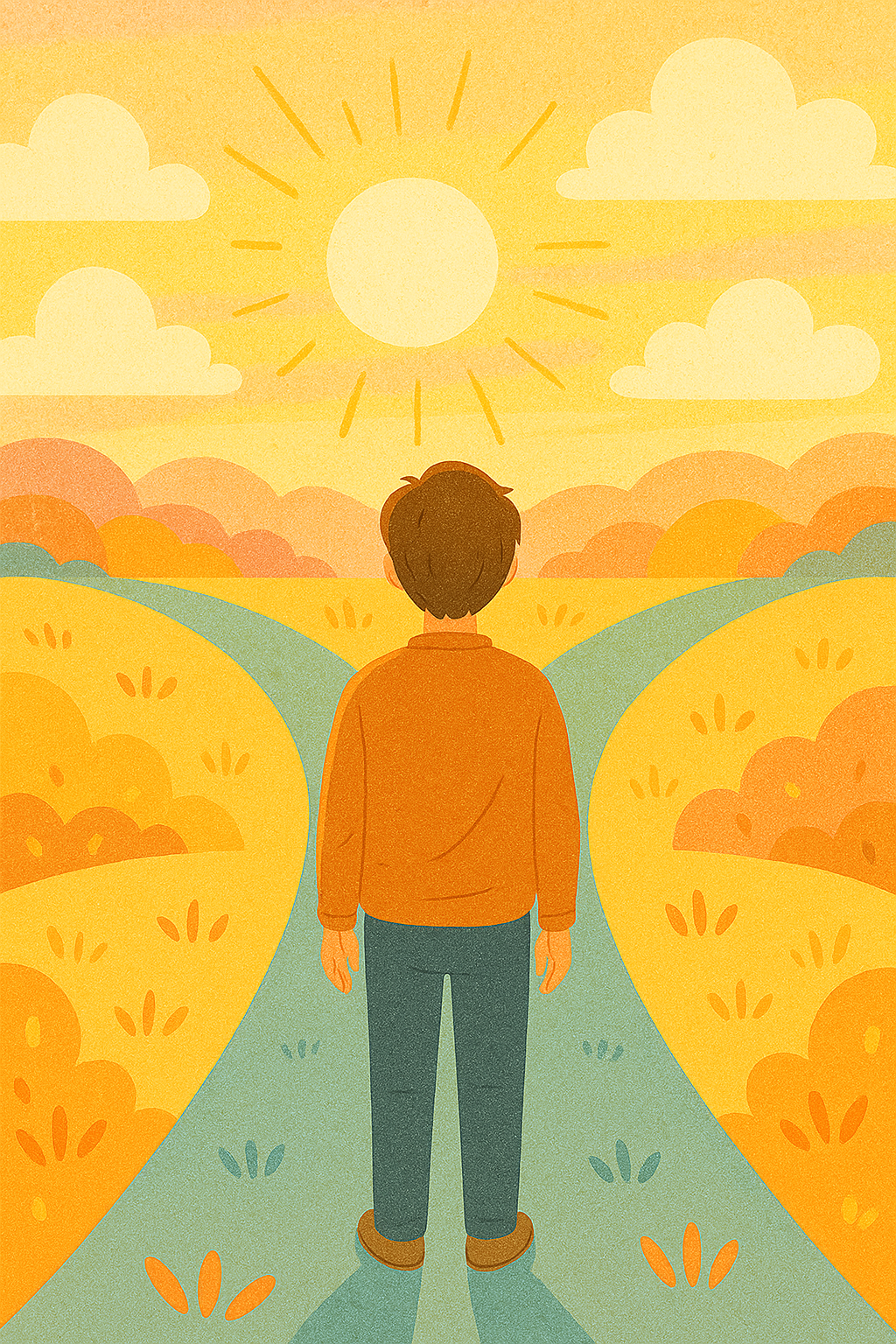🟦 はじめに
- 会議や電話でつい同じ質問を何度もしてしまう──
- 周囲から「また?」と言われ、自分でも理由がわからず苦しくなる──
- 根底にあるのは、過去の失敗が刻まれた「恐怖」が生む「不安」と、
それを乗り越えるための“儀式的確認”、そして周囲のさりげない配慮です。
🟦 本能的恐怖と古典的条件づけの例
- 猫の額を指ではじかれた経験のある猫
猫は「指先ではじく動作=痛い/怖い」という本能的学習が刻まれ、
その仕草を見るだけで体がすくむほどの恐怖を感じます。 - 人間にも同じメカニズムが働く
過去に「聞き逃しで失敗した」「批判された」経験は、
同じ状況で本能レベルの恐怖を再生し、不安を引き起こします。
🟦 恐怖→不安→儀式的確認のメカニズム
| ステップ | 内的プロセス | 行動 |
|---|---|---|
| 1 | 本能的恐怖(失敗体験の残像) | 「またミスしたらどうしよう…」 |
| 2 | 恐怖が不安に変わる | 「本当にこれで合っている?」 |
| 3 | 儀式的確認(記憶/注意障害による) | 同じ質問+データチェックを繰り返す |
| 4 | 一時的安心 | 答えや数値が合うと胸のつかえが下りる |
| 5 | 時間経過で不安再燃 → 再確認 | 新たなズレや変化に気づき、再度確認 |
🟦 記憶障害・注意障害を抱える人の「自信なき確認」
- 「自信を持て」と言われても…
健常者は簡単に「自信を持て」とアドバイスしますが、
記憶障害や注意障害を抱える人にとっては、
「自信を持つ根拠=失敗しなかったという確証」が必要です。 - 儀式としての確認
- 同じデータを何度合計しても結果が微妙に変わる → 「何も信じられない」
- だからこそ確認は“失敗が許されない儀式”となり、一度の確認では安心できない
🟦 自信は「焼け石に水」ではなく「小石の積み重ね」
- 小さな成功体験を重ねる
- 1問ずつ正答できたらチェックリストに✅をつける。
- 「昨日はここまで合っていた」「今日は+αで合っていた」…と
少しずつ自信を積み上げていく。
- 「自信を持て」という一言ではなく、プロセスを共有する
- 周囲は「根拠なき自信」ではなく、「小さな成功の積み重ね」が必要だと理解を。
- 助言する際は「昨日は◯◯まで確認できていたから、今日はもう一歩先までいけるね」と声をかける。
- 安心の儀式に「終わり」を設ける
- 最後に「これで全チェック完了です」と自分で宣言する合図を設定し、
儀式が際限なく続くのを防ぐ。
🟦 具体的コミュニケーション例
- 電話対応時
- 「以前、聞き逃しで大変だったので、まずここまで確認しますね」(恐怖の理由を共有)
- 「これをクリアできたので、次の箇所に進みます」(小さな成功を報告)
- 会議や打ち合わせ
- 資料の該当ページを指しながら「この部分は昨日も合っていたので、安心して先に進みます」
🟦 よくある反論へのさりげないフォロー
| 反論 | さりげない先回り対応 |
|---|---|
| 「うちには関係ないよね?」 | 「実は2024年4月から、すべての民間企業にも“配慮のお願い”ではなく法律での対応が求められるんだ。ちょっと知っておいてくれると助かるかな😊」 |
| 「障害者は迷惑なんじゃ…」 | 「それ、言いづらい話だけど、障害を理由に不当扱いすると法律で禁止されているから、みんなで気を付けてあげてね😉」 |
| 「本人の努力が足りない」 | 「もちろん本人の頑張りも尊重するけど、合理的配慮は個人任せにしちゃダメで、法律に沿って環境を整えてあげることが大切なんだ👍」 |
🟦 まとめ
- 同じ質問を繰り返すのは、過去の失敗体験が刻んだ「本能的恐怖」が生む「不安」と、
記憶/注意障害による“儀式的確認”が原因です。 - 一言の「自信を持て」ではなく、小さな成功を積み重ねるプロセスと、
周囲のさりげない配慮(法律をチラ見せしつつ「わかってあげてね」)が欠かせません。 - まずはこの流れを理解し、自分の儀式を可視化し、周囲と連携して
少しずつ「自信」を育んでいきましょう。