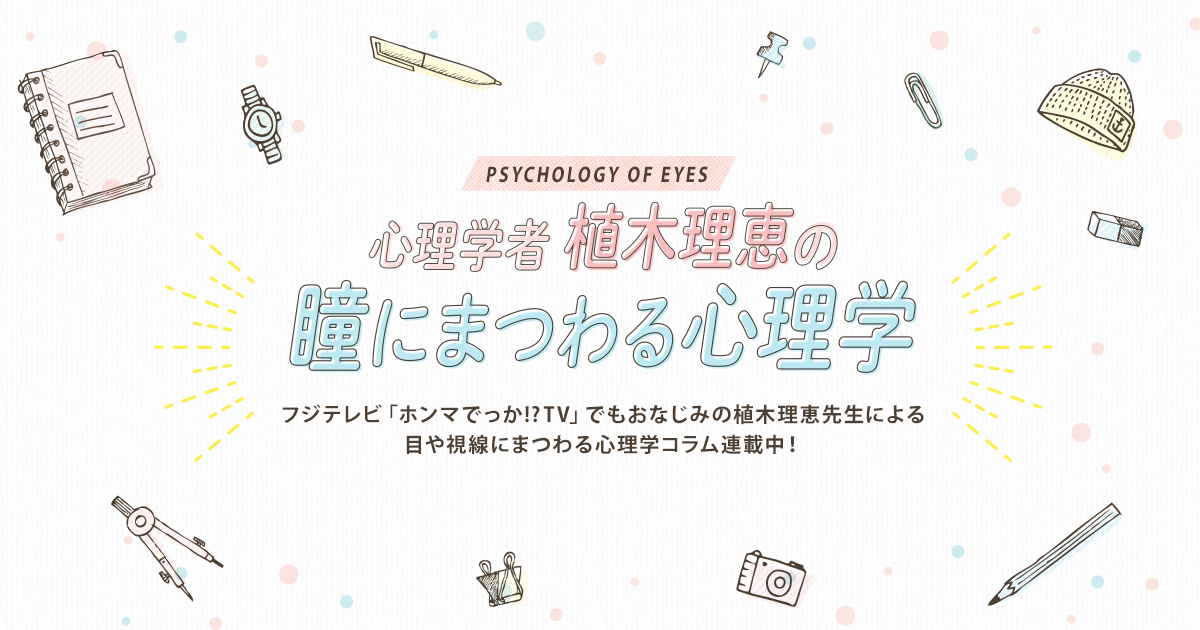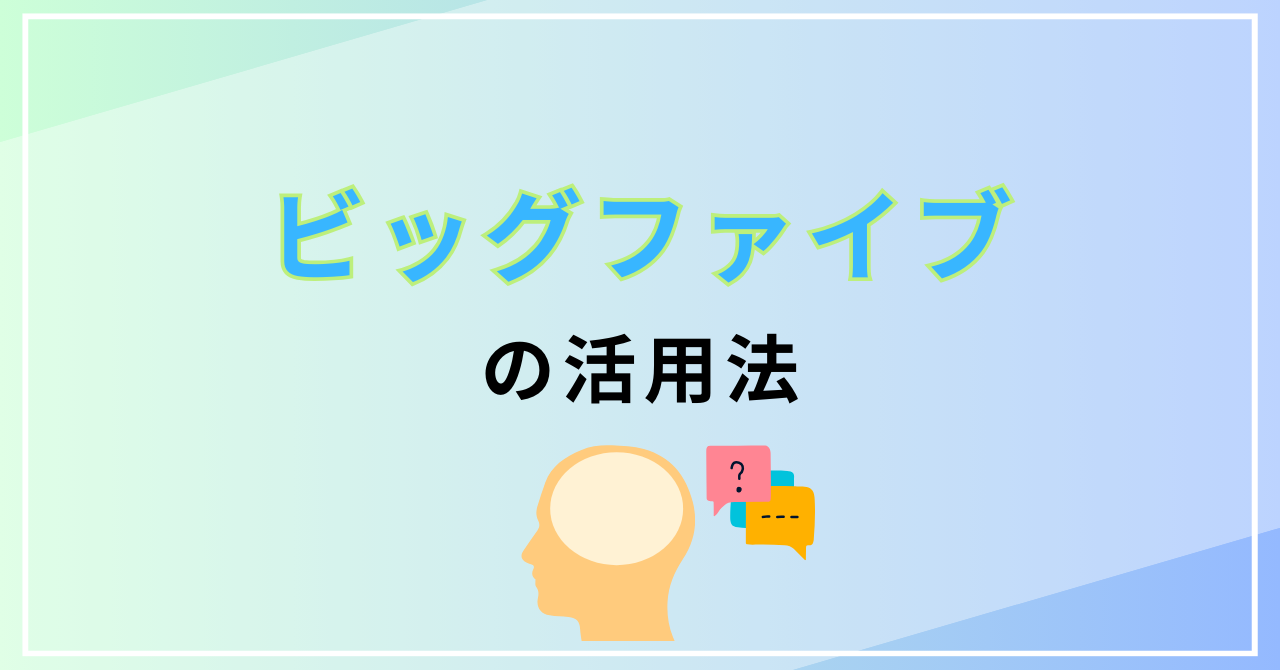はじめに
「他人のふり見て我がふり直せ」
昔から伝えられてきたこの言葉。
私はこれまで、頭では理解していたつもりでした。
しかし、リハビリや就労支援を通じた経験を経て、
初めて本当の意味で「実感」することができました。
今回は、「他人を観察することがなぜ大事なのか」について、私自身の体験を交えながらまとめたいと思います。
他人を観察して気づいた自己理解の難しさ【リハビリ体験】
リハビリ施設でグループリハビリに参加していた頃のことです。
そこには、明らかにグループの中で一番重症に見える方がいました。
しかし、その方はこう言いました。
「私は困っていることなんて何もない」
その瞬間、私は大きな衝撃を受けました。
「どう見ても困っているように見えるのに、本人には困りごとがないと映るのか」と。
そして私は、ふと思いました。
もしかすると、自分も周囲からはそんなふうに見えているのではないか——と。
自分では気づいていないだけで、実際には多くの困りごとを抱えているかもしれない。
このとき、初めて自分の「見え方」と「実際の状態」との間に大きなズレがある可能性に気づかされました。
さらに、グループリハビリでの作業中にも、別の現実を突きつけられました。
リハビリの内容は、最初は「簡単そうだ」と感じていました。
ところが、実際に取り組むとまったくうまくいきませんでした。
- 他の人より作業が遅い
- 作業の正確性が低い
- 作業指示すら覚えていられない
- 最後まで正しく作業を完了できない
私はそれまで、
「他の人は重症そうだ」「私は軽い方だ」
そう思い込んでいました。
しかし実際は、大変そうに見える人たちよりも、自分のほうができない
そんな現実を突きつけられたのです。
自分で自分を正しく評価することの難しさ。
目に見える外見と、内面の実力とは、まったく別物であること。
この体験は、私にとって非常に大きな学びとなりました。
メモを通じて学んだ自己客観視の重要性【就労支援体験】
就労支援施設での出来事も、私に深い気づきをもたらしました。
ある日、他の人たちが取っているメモを何気なく目にする機会がありました。
そこには、私のメモの何倍、何十倍もの情報が、びっしりと書き込まれていました。
そのとき、また私は思い知らされました。
「私は井の中の蛙だった」と。
これまで自分では、「しっかりできている」と思い込んでいた。
経験や実績に誇りを持っていた。
しかし、実際にはごく当たり前のことすら十分にできていなかったのです。
以前、職業適性検査を受けた際にも指摘されていました。
「自己評価が高すぎる」と。
できないことを、工夫してできるように「見せて」しまう。
それが周囲の期待を過剰に引き上げ、やがて自分を苦しめる結果になる。
そんな悪循環に、私は何度も陥っていたのだと、改めて気づきました。
慢心を防ぐために意識したこと【自己成長への気づき】
さらに、運転免許を再取得する際、医師から言われた言葉が心に残っています。
「疲れと慢心に気をつけなさい」
私はこの二つを、日々自分に言い聞かせるようになりました。
——疲労による注意力の低下。
——「もう大丈夫だろう」という慢心。
意識していても、ふとした瞬間に顔を出してしまう。
それが、怖い。
幸いにも大きなトラブルには至っていませんが、
それは単に運が良かっただけかもしれません。
そう考えると、今も気を抜くことはできないと強く感じています。
他人を観察することは自己理解を深める最短ルート
自分ひとりで自分を正確に理解するのは、とても難しいことです。
理想を言えば、誰かから客観的な評価を受けるのが一番です。
しかし、それには信頼や環境など多くの条件が必要で、簡単には手に入りません。
だからこそ、
「他人を観察する」ことが、今すぐできる最も現実的な自己理解の手段だと私は考えます。
「他人のふり見て我がふり直せ」
この言葉は、今の私にとって単なる格言ではありません。
日々を生きるための、確かな指針になっています。
おわりに
これからも私は、周囲の人たちをよく観察しながら、
自分の振る舞いや考え方を少しずつ見直していきたいと思います。
「自分を過信しない」
「常に学び続ける」
そんな姿勢を持ち続けることで、
少しずつでも成長していけたら——
それが今の私の目標です。