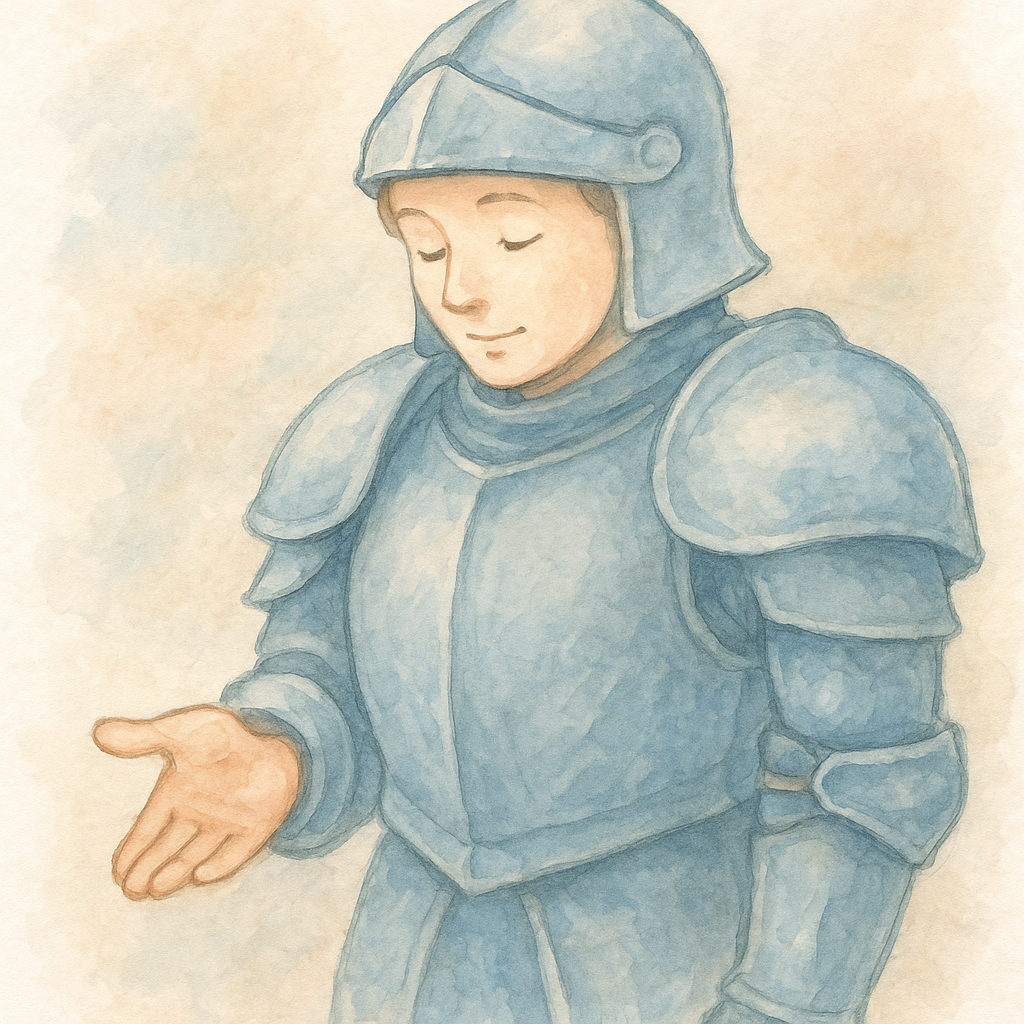はじめに
障害や病気を抱えて暮らしていると、日々の生活や仕事の中で「配慮」や「助け」をお願いしなければならない場面がどうしても増えてきます。
しかし、その「お願い」がいつもすんなり受け止められるわけではありません。
「わがまま」だと誤解されたり、「またか」と思われてしまうこともあります。
この記事では「お願いする側」の苦悩を中心に書いてきましたが、一方で「受け止める側」の事情や限界も大切にしたいと思います。
「お願い」が“わがまま”と受け取られる現実
本当は頼みたくない。自分でできることはできるだけ自分でやっている。
それでもどうしても「ここだけは無理」という場面が出てくることがあります。
ですが、配慮の線引きは非常に難しく、どこまでが“最低限”で、どこからが“過剰”なのかは、受け止める側の事情や価値観によっても変わります。
「自分は忙しい」「余裕がある人がやればいい」「負担を増やしたくない」――そう感じる人がいるのも自然なことです。
全ての人が何らかの困難や事情を抱えていますし、配慮が過剰になると「公平性」や「依存」をめぐる懸念も生まれます。
社会のリソースにも限界があり、すべてのお願いに応えることは現実的ではありません。
「社会全体のため」や「お互い様」は伝わりにくい
「配慮」や「助け合い」は社会全体にとっても大切――そう頭で理解していても、
日々の忙しさや自分自身の事情が優先されると、「今この場で自分が得する話じゃないとピンとこない」という気持ちもよく分かります。
大きな理屈よりも、現場での“実感”や“損得”の方が重く感じられるのは、ごく自然なことかもしれません。
それでも「配慮」をお願いし続ける理由
配慮は“特別扱い”でも“贅沢”でもなく、“生きるための最低限のセーフティネット”だと感じています。
「できないこと」は「やりたくない」からではなく、どれだけ努力しても越えられない「壁」がある――そういった現実が背景にあります。
とはいえ、お願いの数が多くなればなるほど、「甘え」や「依存」への懸念を抱かせてしまうことも否めません。
「自分でできることは自分でやる」という姿勢と、「本当にどうしても無理な部分」の線引きを、
できるだけ具体的に、誠実に伝えていくことが大切だと感じています。
「めんどうくさい」と思われる、お願いする側の葛藤
お願いする側も「これ以上お願いしたら嫌われるかもしれない」「わがままだと思われたくない」と悩みます。
伝え方一つで、受け取る側の気持ちも大きく変わると感じています。
「できない」と伝えるだけでなく、「ここはこうしてもらえると助かる」「これなら自分でもできる」といった具体的な協力案や、
助けてもらったときには「感謝の気持ち」をきちんと伝える――そうしたコミュニケーションも大切にしたいと思います。
「受け止める」の範囲は、人によって大きく異なる
お願いを伝えても、「話を聞いてくれる」「うなずいてくれる」だけの人もいれば、
気持ちを理解しようと質問してくれる人、実際に具体的な行動を起こしてくれる人もいます。
どこまでを「受け止めてくれた」と感じるかは、お互いにズレが生まれやすいポイントですし、
状況によっては「無理に背負わないでほしい」という相手の気持ちも尊重したいと思います。
主張が強くなるのは「心がズタボロになった証」かもしれない
SNSなどで、ときに主張の強い当事者を見かけることがあります。
もしかするとそれは、何度もお願いし、否定され、傷ついた末に――「自分を守るための防衛反応」として“心の鎧”をまとうようになった姿なのかもしれません。
けれど、強い言葉が逆に誤解や孤立を生みやすいことも確かです。
「どうしても伝えたい」という思いが、かえって距離を作ってしまうこともある――
だからこそ、自分自身も時に立ち止まり、伝え方や態度に気を配ることが必要だと感じます。
それでも「伝えること」をあきらめない理由
みんなに届くとは限りませんが、必ず“分かろうとしてくれる人”はいます。
伝えなければ、その可能性も生まれません。
また、「どこまでが自分の努力で、どこからが“本当にお願いしないと無理”なのか」を言葉にしておくことは、自分自身を守ることにもつながります。
そして、「わかってくれる人」と出会えたとき、初めて心から安心できる瞬間が訪れるのだと思います。
おわりに
“お願い”や“配慮”は「甘え」ではなく、「努力の果てのSOS」です。
どこまでお願いしていいか悩む気持ち、お願いを受け止める側の戸惑い――
その両方を想像し合える世の中が、きっと少しずつ、優しくなっていくはずです。