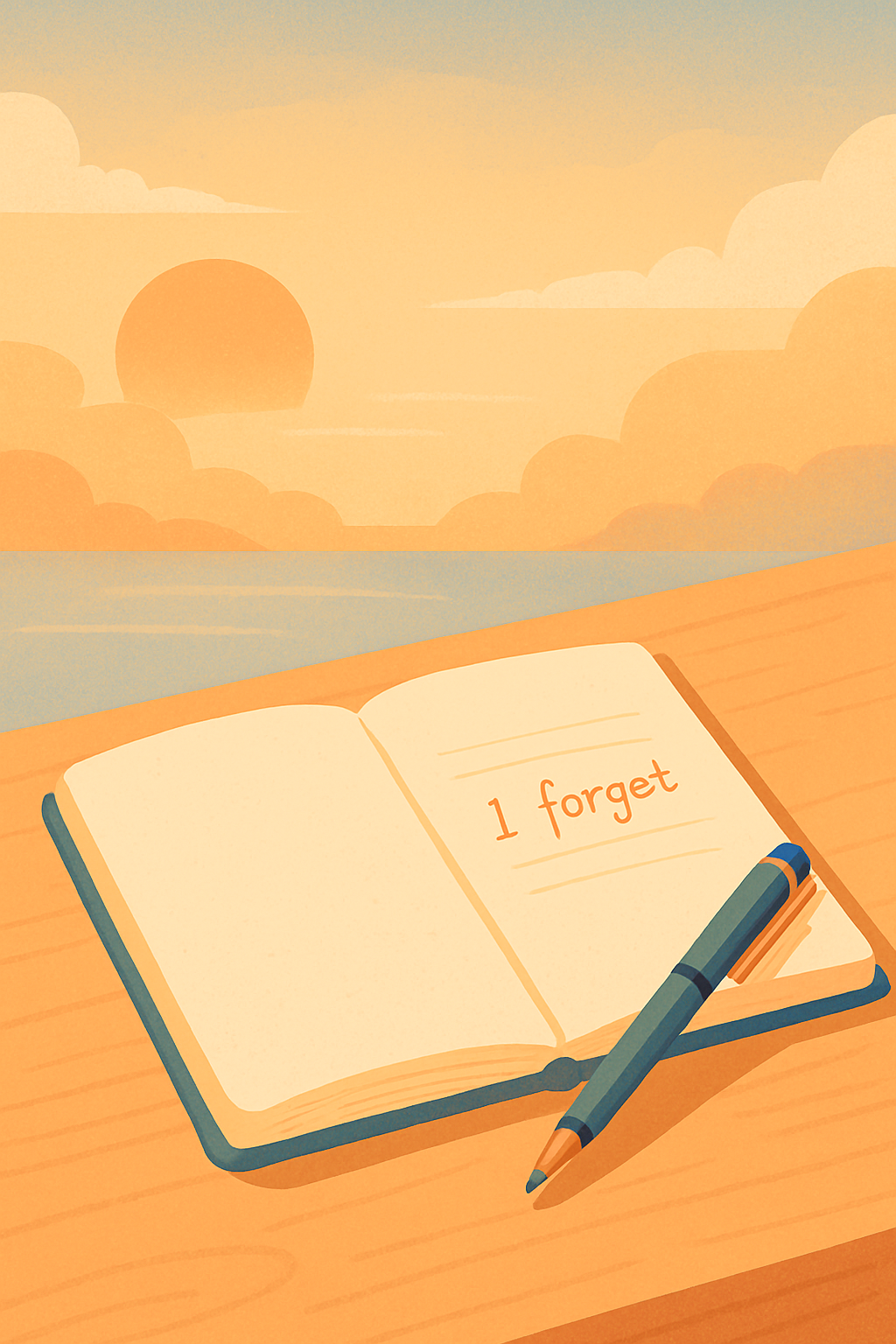なぜ“あの日のこと”を忘れていたのか?
──高次脳機能障害の私が気づいた記憶のしくみ
「忘れた」というより「思い出せない」
高次脳機能障害を抱える私にとって、「忘れる」という出来事はもはや日常茶飯事です。
特に夕方以降は、ほとんど何も思い出せなくなります。
正確に言うなら、「忘れた」わけでもなく、「思い出せない」。
そもそも、その出来事があったこと自体を思い出せないのです。
イレギュラーや新ルールに弱い脳のクセ
毎日のルーチンに組み込まれていない“イレギュラーな出来事”に、私はとても弱いです。
たとえば、「今日からこの手順が変わります」と言われても、いつの間にか記憶は“巻き戻って”、以前のルールに従って行動してしまう。
しかも、その行動が正しいと思い込んでいるために、間違いにすら気づかない。確認漏れが多いのはこのためです。
「確認すればいい」と思う人へ
よく「確認すればミスは防げる」と言う人がいます。でも、それは“確認する”という発想が自然に出てくる人の話です。
たとえば、パンを食べるときに「どうやって食べるんだっけ?」と確認しますか?
スマホを使うたびにマニュアルを読みますか?
しませんよね。当たり前だから。
私にとっても、“以前できていたこと”は当たり前になっている。
だからこそ「確認しよう」という発想すら浮かばない。
そしてミスが起こる。でも、これは“だらしない”とか“注意力がない”ではないんです。
そういうレベルで、記憶が抜け落ちるのです。
初期はショックだった。今は“あきらめ”も対策のうち
最初のころは正直ショックでした。
「直らないのか」「なんとかしなきゃ」と思い、
・高次脳機能バランサー
・パズル
・ナンプレ
など、あらゆる脳トレを試してみました。とにかく、やり続けました。
でも、効果があったかどうかは正直わかりません。
むしろ、「どういう時に忘れやすいか」を絞り込むことの方が、意味がある気がしています。
- 忘れやすい時間帯を避ける
- 疲れる前に大事なことを済ませる
- 生活リズムを記憶の波に合わせてみる
そんな風に、“忘れる”前提での対策を考えるようになりました。
「やっぱり忘れちゃう」──それでいい
最近では、「あ、やっぱり忘れちゃったね」とのほほんと自分から言えるようになりました。
周囲も理解してくれていて、最初から「忘れる前提」で動いてくれます。
そうなると、忘れても困らない仕組みの中で生活ができる。
困らなければ、それはもう“障害”じゃない。
そんな風に、私は少しずつ自分の生活と気持ちを調整しています。
最後に:忘れることは「悪」ではない
「忘れる」こと自体が悪なのではありません。
問題は、「忘れる前提」がないまま生活が進むこと。
それが、誤解や失敗、そして自己否定につながるのです。
だから私は、これからも「忘れてもいい状況」を作ることに力を入れます。
そして、“忘れることを恐れない”生き方を選んでいきたいと思います。
※「記憶されていない」のではなく「思い出せない」──その前提で、私は“再起動できる仕掛け”を考えるようになりました。